老人脳
歳をとっていくことには抗えない。しかし、脳はいつまでも若々しく保てます。
今回ご紹介する書籍は、「80歳でも脳が老化しない人がやっていること」西剛志(にし たけゆき)著、アスコムより出版されています。
脳の老化で、「老人脳」と呼ばれる状態になると、周りが気にならなくなる、記憶が曖昧になる、同じ主張を繰り返す、感情的になる。脳が老化するとこの様な現象が起きます。
一方で、80代や90代になってもどんどん新しいことに挑戦し、元気に前向きに若々しく生きている、そういう人は「スーパーエイジャー」と呼ばれています。
スーパーエイジャーになる人と老人脳になる人の差は、いったいどこにあるのか?それが今回のテーマです。
結論から言えば、面倒くさがらず常に脳に新しい良い刺激を与え続けることです。
廃用症候群の症状の種類
廃用症候群や廃用性萎縮という言葉があります。これは、体を動かさないことにより生じるさまざまな機能低下のことを言います。
廃用症候群の一例としてその症状を以下に示します。
- 筋萎縮・・・筋線維が細くやせ衰え、筋肉の柔軟性や筋力も低下する(フレイル)
- 骨萎縮・・・骨密度が低下し、骨がもろくなる、骨が変形する(脊柱管狭窄症など)
- 関節拘縮・・・関節の軟部組織が線維化し関節可動域が減少(腰痛・股関節痛・膝痛など)
この様に身体の各部位は、常に使い続け動かしてあげないと、機能が低下して使えなくなってしまうのです。これは脳の神経細胞も同じで、使わなくなったところから、だんだんと委縮してしまうのです。
つまり、筋肉でも関節でも、脳神経でも常に新たな刺激をし続けなくてはいけないということです。楽をしすぎることは、刺激量が減る事であり、その結果、機能低下が進んでしまうのです。
老人脳は後天的なものであり、日々の様々な習慣(思考×行動)の積み重ねによって変えることができる。習慣を変えることで老人脳を遠ざけることができる。
廃用症候群にならないためにカイロプラクティックやオステオパシー、整体などで体のバランスを整えることも大変有効です。体操や運動を始めるにあたり、関節や筋肉のバランスが良い状態に調整しておくと効果的に運動が行えます。
タラントのたとえ
マタイ25章14~30節に個々の人間に与えられた能力と、その使い方についてのたとえ話があります。
25:14 天の御国は、旅に出るにあたり、自分のしもべたちを呼んで財産を預ける人のようです。
25:15 彼はそれぞれの能力に応じて、一人には五タラント、一人には二タラント、もう一人には一タラントを渡して旅に出かけた。するとすぐに、
25:16 五タラント預かった者は出て行って、それで商売をし、ほかに五タラントをもうけた。
25:17 同じように、二タラント預かった者もほかに二タラントをもうけた。
25:18 一方、一タラント預かった者は出て行って地面に穴を掘り、主人の金を隠した。
25:19 さて、かなりの時がたってから、しもべたちの主人が帰って来て彼らと清算をした。
25:20 すると、五タラント預かった者が進み出て、もう五タラントを差し出して言った。『ご主人様。私に五タラント預けてくださいましたが、ご覧ください、私はほかに五タラントをもうけました。』
25:21 主人は彼に言った。『よくやった。良い忠実なしもべだ。おまえはわずかな物に忠実だったから、多くの物を任せよう。主人の喜びをともに喜んでくれ。』
25:22 二タラントの者も進み出て言った。『ご主人様。私に二タラント預けてくださいましたが、ご覧ください、ほかに二タラントをもうけました。』
25:23 主人は彼に言った。『よくやった。良い忠実なしもべだ。おまえはわずかな物に忠実だったから、多くの物を任せよう。主人の喜びをともに喜んでくれ。』
25:24 一タラント預かっていた者も進み出ていった。『ご主人様。あなた様は蒔かなかったところから刈り取り、散らさなかったところからかき集める、厳しい方だと分かっていました。
25:25 それで私は怖くなり、出て行って、あなた様の一タラントを地の中に隠しておきました。ご覧ください、これがあなた様の物です。』
25:26 しかし、主人は彼に答えた。『悪い、怠け者のしもべだ。私が蒔かなかったところから刈り取り、散らさなかったところからかき集めると分かっていたというのか。
25:27 それなら、おまえは私の金を銀行に預けておくべきだった。そうすれば、私が帰って来たとき、私の物を利息とともに返してもらえたのに。
25:28 だから、そのタラントを彼から取り上げて、十タラント持っている者に与えよ。
25:29 だれでも持っている者は与えられてもっと豊かになり、持っていない者は持っている物までも取り上げられるのだ。
25:30 この役に立たないしもべは外の暗闇に追い出せ。そこで泣いて歯ぎしりするのだ。』
人は、それぞれ何がしかの能力を与えられています。しかし、失敗を恐れ消極的になって使わなければ、それらを失ってしまいます。
因みに、芸能人を「タレント」と呼びませんが、その語源は、このタラントなのです。才能や能力は一人一人違いますが、それをどう使い活かすかが大切なのです。
脳も筋肉も与えられた機能を出し惜しみしていると、機能低下が進んでしまいます。体はその異常を痛みやしびれで教えてくれます。首の痛みや腰痛もこのような結果起こる場合もあるのです。
脳のピーク
- 情報処理能力のピーク・・・18歳
- 人の名前を覚える力のピーク・・・22歳
- 顔を覚える力のピーク・・・32歳
- 集中力のピーク・・・43歳
- 相手の気持ちを読む力のピーク・・・48歳
- 語彙力のピーク・・・67歳
脳と睡眠
質の高い睡眠をとることは、脳にとっても大切で、アルツハイマー型認知症の原因は、脳のごみであるアミロイドβですが、このアミロイドβはいい睡眠によって消去されるのです。
成人のベストな睡眠時間は、6~7時間といわれますが、加齢とともに必要な睡眠時間が少なくなるといわれます。睡眠時間は10歳毎に10分短くなるのです。ですから、20歳よりも70歳の方が50分ほど睡眠時間が短くなるのです。
より良い睡眠をとるには次の三つが大切といわれます。
- 30分未満の昼寝・・・昼寝を30分未満する習慣がある人は、昼寝をしない人に比べて認知症のリスクが50%も下がる。
- いびきを改善・・・いびきをかく人は睡眠時無呼吸症、もしくはその予備軍の可能性があります。これらの人は認知症の発症リスクが1.8倍。いびき対策としては横向き寝がおすすめです。
- 歯を大切にする・・・歯が20本以上あると、いい睡眠がとりやすい。歯が少ないと、睡眠時に歯をかみ合わせることができないため、気道が締まりやすくなり、睡眠中の呼吸を妨げる。
寝ることは、骨や関節にとっても必要で、昔から「骨休め」と言われますが、横になることで重力から解放され骨や関節にかかる圧力を軽減できます。
デスクワークなどで長時間座り続けると、腰椎椎間板に過剰な圧がかかり続けます。このような状態が長期間続くと腰椎椎間板ヘルニアなどになってしまうこともあるので注意が必要です。
無理をすると脳は老化する
無理をすると脳はストレスを感じ、そのストレスが脳の老化を早める。ただし、怠けすぎたり、ダラダラと楽をしすぎるのも脳にはマイナスです。
「中庸」が一番エネルギーが高い状態。このバランスが崩れると病気になったり、メンタルがやられたりします。
脳のバランスだけでなく、体のバランスが崩れることも、脳を老化させる原因になります。体の歪みもある意味、無理をしてきた結果なのです。無理のないバランスの良い体の使い方であれば、故障もしづらく、歪みも起こりにくいのです。
整体やカイロプラクティック・オステオパシーなどで身体のバランスを整えることは、脳によい刺激を入力する働きがあるので大変有効な手段なのです。
休め遺伝子
中高年にしか存在しない「休め遺伝子」が脳の損傷を守る。「長寿遺伝子」中から「レスト(REST)遺伝子」というものが発見されました。
これはRESTというタンパクのことで、本来の意味とは違うのですが、この遺伝子が脳をダメージから守ってくれるのです。
2019年、ハーバード大学の研究チームが、脳バンクに提供された高齢者の脳を調べたところ、100歳以上の人の脳には70~80歳で亡くなった人よりも「レスト」という遺伝子がたくさん発現していました。
休め遺伝子は脳活動の過剰な活性化を抑える役割があって、体全体の活動をゆるやかにして負担をかけないことで、脳の寿命を伸ばす効果が世界的に注目されています。
脳を活性化するために新しいことに挑戦したり、新しい人間関係をつくることは、おすすめですが「やりすぎ」は禁物です。
脳の活性化は大切ですが「過剰な活性化」は抑えなければなりません。そこにブレーキをかけるのが休め遺伝子です。
中高年になって「情熱ややる気が薄れるのは自分のせいではなく遺伝子のせい」そのくらいに思っておく方がいいのかもしれません。
レスト遺伝子はじめ長寿遺伝子の役目の一つは「自分を大切にすること」です。頑張りすぎも、甘やかしすぎも逆効果で「中庸」が大切になります。
脳の老化
脳の神経細胞は70歳を超えても新しく生まれるだけでなく、90歳になっても神経細胞が再生されています。
脳の老化の診断法
「片足立ち診断法」・・・目を閉じた状態で片足立ちをして何秒間、片足で立っていられるか計ってください。
なお転倒の恐れがありますので、くれぐれも無理のないようにし、またできるだけ周りに障害物がない場所でやって下さい。
目安は30秒です。目を閉じて30秒以上、片足で立っていられれば、脳はまだ若い状態です。逆に30秒未満の人は、老人脳が進んでいます。
- 平均58.8秒・・・脳年齢30代
- 平均32.9秒・・・脳年齢40代
- 平均23.7秒・・・脳年齢50代
- 平均9.4秒・・・脳年齢60代
- 平均4.5秒・・・脳年齢70代
- 平均2.9秒・・・脳年齢80代
(※国立長寿医療研究センターによる年代別平均値で、30代については個別に50名の平均値を算出)
両眼を開いたままで片足立ちをして、20秒以上続けられない場合は、小さな脳出血を発症している「無症候性ラクナ梗塞」などの可能性があるので注意が必要です。
平衡感覚は目を開けているときは視覚野でバランスをとろうとします。目を閉じると、視覚情報ではなく「本当の身体バランス感覚」で立とうとします。この「本当の身体バランス感覚」が脳の状態と比例しているのです。
老人脳の5つのタイプ
- やる気脳の老化・・・あらゆる意欲の低下、集中力の低下、流行についていけない、昔のことばかり懐かしむ、過去にすがりたくなる
- 記憶脳の老化・・・物忘れが増える、人の顔や名前が覚えられない、同じことを何度も言う、「あれ、あれ」という言葉がよく出てくる、昨日食べたものがなかなか思い出せない
- 客観・抑制脳の老化・・・感情を抑制できない、その場の空気にのまれやすい、リスクを考えなくなる、情報を鵜呑みにする、運転ミスが増える、客観視ができない、オレオレ詐欺にあいやすい
- 共感脳の老化・・・人の話を聞かない
- 聴覚脳の老化・・・人の声が聞きづらい、テレビのボリュームを大きく上げないと聞こえない
老人脳にならないための運動
脳の認知機能を一番高める運動は「コーディネーション運動」とよばれるもので、ドリブル、平均台、ボールを上に上げて手を1回たたく、お手玉、卓球などバランスをとる運動のことです。
また、ダンスは脳活の極みといわれ、You Tube動画などを見ながら、それに合わせて踊ることは大変良い脳への刺激となります。
ウォーキングなどの様に、単調な繰り返しの運動よりも、変化に富んだ運動の方が脳への刺激が多く効果的なのです。
老人脳にならないマインド
自分は若いと本気で思うだけで、脳も体も若くなります。少し古い調査ですが、アメリカのハーバード大学でこんな実験がありました。70代になる8人が22年前の内装に仕上げた建物の中で5日間共同生活をするというものです。
内装だけでなくテレビは当時の白黒テレビ、ラジオからは当時人気があった歌が流れてくる。本棚の本などもすべて22年前にして、5日間暮らしたわけです。
そして、こんなルールを定めました。
- 22年前の自分になりきる
- 当時の話は全て現在の出来事として語る
- 自分の写真や家族の写真は22年以前のものを飾る
そして、この実験から驚きの結果が出たのです。
- 手先の器用さが向上した
- 姿勢が良くなった
- 視力がアップした
- 見た目が若くなった
- 考え方が柔らかくなった
また、若く見えるようにしただけで、血圧まで下がったという実験もあります。
逆に、脳にとってのNGワードがあります。「老けた」「歳をとった」「もう若くない」です。
そして、自分の年齢に対して実年齢よりも8~13歳高く感じている人は、死亡リスクや病気リスクが通常より18~35%高かったというのです。
ミジンコの長寿
以前、あるテレビ番組に坂田 明(さかた あきら)さんが出演しミジンコのお話をしていたのを覚えています。坂田 明さんは、日本のジャズ・サクソフォーン奏者、タレント、俳優と幅広くご活躍され、更にミジンコ研究家としても有名な方です。
坂田さんがミジンコを飼育した際に、ある方法を行うとミジンコの寿命が延びるというのです。それはどのような方法かといえば、お母さんミジンコは子供を産んだあとしばらくすると、その役目を終えて死んでしまうそうです。
ところが、その子供たちをスポイトで全部吸い取って別の容器に移してしまうと、お母さんミジンコはまた子供を産むため頑張って生きるそうです。
そしてまた、その子供を別の容器の移してしまうと、お母さんミジンコはさらに頑張って生きてまた子供を産むというのです。
こうしてお母さんミジンコは、子孫を残すという役割を全うしようとして、本来の寿命よりも長く生き続けたというのです。
私たち人間も、目的意識や意志、使命などをしっかりもって生きていくことが大切であると小さなミジンコから教えられた思いです。
脳の老化スピードの速い人がよく使う言葉

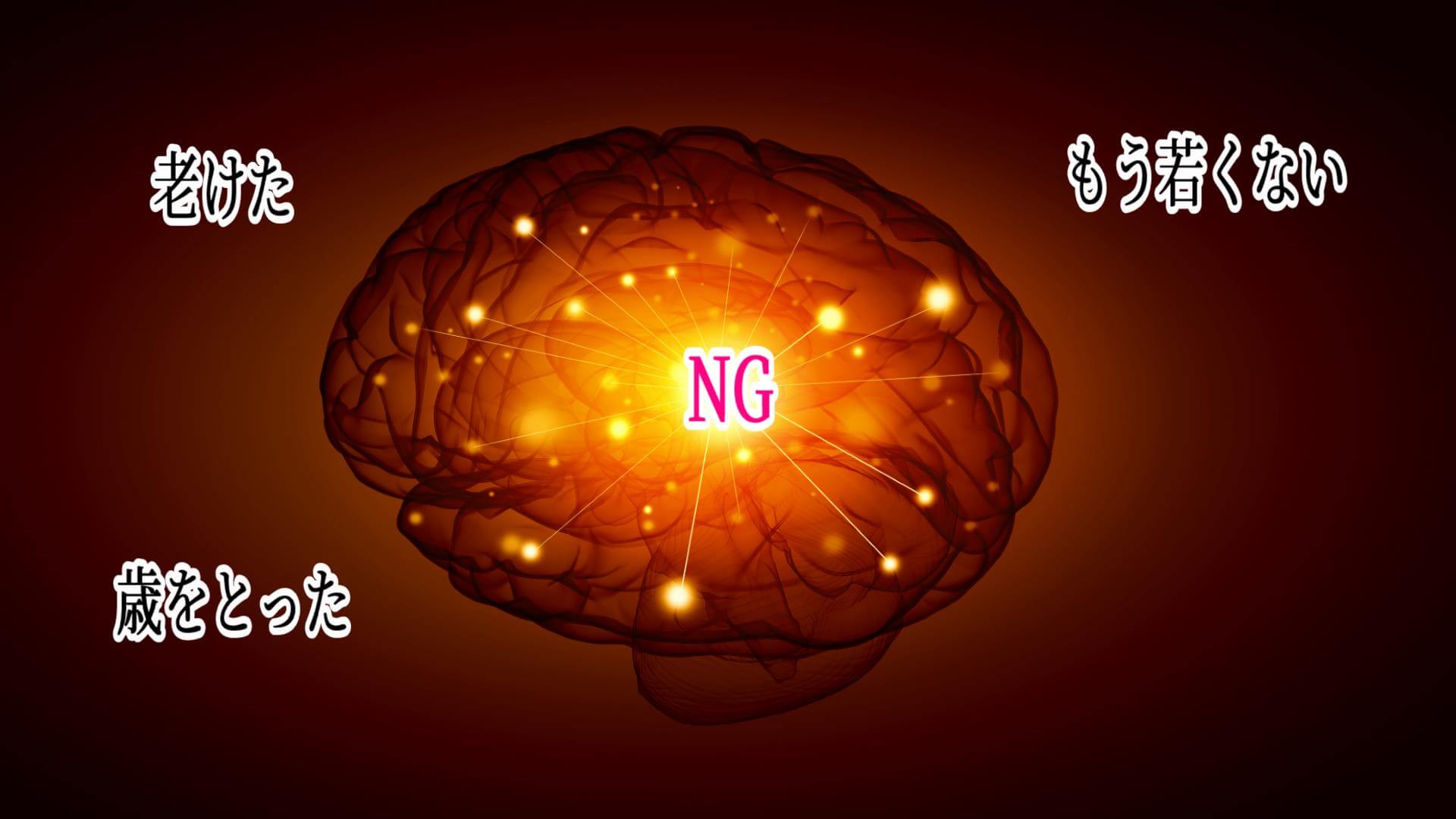
脳だけでなく人生にも悪い影響を及ぼす言葉があります。これは「脳のプライミング効果」と呼ばれるものです。
脳にマイナスになる「使わない方がいい言葉」を以下に示します。
| 疲れた | あの人のせいだ |
| 嫌だ | あのときはよかった |
| 運が悪い | ~しなければいけない |
| できない | 体力がない |
| 難しい | 気力がない |
| わからない | いつも私は~ |
| 無理 | みんな~と言っているから |
| もう歳だから | 歳をとると~ |
| 時間がないから | 面倒くさい |
「あー、疲れた」「もう、嫌になる!」「そんなことできるわけない」などの言葉を日ごろ何気なく使っていると、脳の老化スピードが速くなってしまうのです。
ニューヨーク大学の実験で、学生を2つのグループに分け一つ目のグループは、年配者のような言葉を使ってもらい、もう一つのグループには、ニュートラルな言葉を使ってもらいました。
その結果、年配者のような言葉を使ったグループメンバーの歩くスピードが遅くなってしまったのです。
この実験からわかることは、使った言葉がその後の行動に影響を与えるということです。
中村天風師も「人生は心一つの置きどころ」と述べていました。積極的観念を潜在意識に送るために、言葉使いの重要性を力説しています。消極的な言葉――「困った」「弱った」「情けない」「悲しい」「腹が立つ」といった言葉は、天風会では禁句となっており、これらの言葉を使うことを厳しく戒めています。
昔の良かったことを思い出すことは脳の栄養
幸福度が高い人を調べていくと「過去の楽しい思い出を振り替える頻度が高い」ということがわかりました。
病気の快復率は楽しいことを振り返ると早まるのです。脳科学では過去と未来を考える脳の回路は同じです。未来を考えるときも、過去を振り返っているときも、同じ脳の回路を使っています。
ですから、過去をマイナスに考えると、未来もマイナスに考えてしまう。逆に過去をプラス、楽しい、幸せと考えると、未来もプラス、楽しい、幸せと考えることができるのです。
まとめ
いつまでも脳を若く保つためには、前向きで明るい精神状態で、めんどうがらずに常に新しいことにチャレンジすることで、脳に良い刺激を入れ続けることです。
よく噛むこともそうで、楽をして柔らかいものばかりを食べるのではなく、硬いものもしっかり噛むことで脳が刺激されます。
今まで通ったことのない道を歩いたり、運動でもトレーニングの種目に変化をつけたり、強度を変えることで、「プラトー」と呼ばれる停滞期を打破できます。
骨でも筋肉でも使わなければ弱くなります。脳も同じで、楽ばかりして刺激がマンネリ化してしまうと、退化してしまいます。
何歳になっても挑戦する心を失わないようにしましょう!
================================
肩こり・腰痛・坐骨神経痛・椎間板ヘルニア・ぎっくり腰・めまい・頭痛・脊柱管狭窄症・自律神経失調症・五十肩・膝の痛み、股関節の痛み等、様々な症状の根本原因を施術する整体治療院 。あん摩・マッサージ・指圧師の国家資格取得者「札幌 キネシオロジーの谷井治療室」です。
全国どこでも遠隔施術も承ります。https://www.taniithiryousitu.com/distant-healing/
札幌市営地下鉄中島公園駅から徒歩1分と好アクセスです。
ご予約は TEL: 011-211-4857 にお電話下さい。
腰痛や肩こりの改善なら札幌市の整体|国家資格あん摩マッサージ指圧師の谷井治療室トップページへ
北海道札幌市中央区南9条西4丁目3-15AMSタワー中島1503号室
健康と医療ランキング
にほんブログ村
